特許情報の歴史とJPDSサービスの変遷
特許制度のはじまり
特許法のはじまりから公報の電子化までの間、特許調査は紙公報を1枚ずつ手でめくって必要な情報を探したり、パンチカードやマイクロフィルム等の技術を利用して情報の整理、抽出、確認をしていました。
1885年
専売特許条例の公布(日本の特許制度の始まり)
1959年
特許法、実用新案法、意匠法、商標法改正
1971年
出願公開制度の導入
1988年
特許情報の国内外提供を目的として日本パテントデータサービス(株)設立
創業当時は特許情報の輸出入がメイン事業であり、 海外では日本の特許情報を、国内では海外の特許情報を販売していました。
その中で歴訪した欧米諸国で海外の特許情報電子化の流れを肌で感じることで、日本の電子化時にすぐにサービス展開を実施できました。
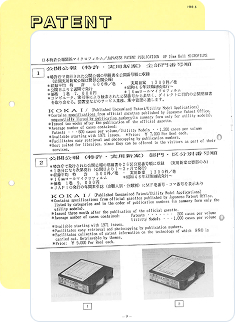
1989年
マイクロフィルムカタログ

WIPOフェア出展

ESPACEと端末
公報の電子化
特許情報が電子データとして発行されるようになり、CD-ROM等での提供や、PCでの特許情報検索が可能となりました。
1992年
電子特許公報検索システム「JP-ROM」発表
日本の特許情報の電子化を受けて、「JP-ROM」「特許公報CD-ROM」の販売を開始。積極的な利用提案とソフトウェアの高評価によって、事業を大きく伸ばしました。
このころから、業務の効率化につながる検索・印刷の評価は高く、今でもこの考え方は引き継がれています。

特許公報CD-ROM等製品
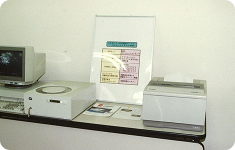
IBM・トーキンと共同で開発した
光磁気ディスクオートチェンジャー
1993年
特許情報の電子化
インターネットでの特許検索の開始
インターネットの普及により、IPDL、JP-NET等の特許検索サービスが提供されるようになりました。
1999年
特許庁が特許電子図書館サービス(IPDL)開始
商標出願公開制度の新設
2000年
意匠・商標情報の電子化
2000年
インターネット特許検索「JP-NET」の本格サービス開始
CDからインターネットへの移行をいち早く実施した、インターネット特許情報検索サービス「JP-NET」は多くの方にご利用いただき、現在も幅広くご活用いただいております。
2000年には500万件の特許情報が蓄積されていました。
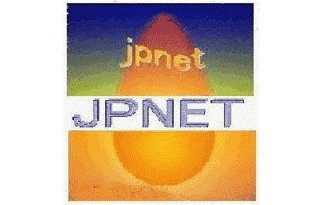
JP-NETサービス開始当時イメージ
2003年
特許・実用新案の出願フォーマットの国際標準化(XML化)
2003年
インターネット特許検索「NewCSS」サービスを開始
2005年
特許分析・マップソフト「ぱっとマイニングJP」を販売開始
2013年
「PATAS」事業を譲受・知財システム開発(株)設立
キーウェアソリューションズ(株)より、特許管理システム「PATAS」事業を譲受。特許管理システム事業に参入すると共に、開発会社として知財システム開発(株)を設立しました。
主力サービスの「JP-NET/NewCSS」との連携の強化に取り組み、システム間の情報連携が重要になる時代に移ってきました。

PATAS事業譲渡当時イメージ①

PATAS事業譲渡当時イメージ②
インターネットの高速・大容量化
インターネットの高速・大容量化により、高機能なサービスやクラウドサービスが普及し始めます。
また、経過情報データの切り替えや、公報システム刷新による公報の毎日発行への切り替え等、特許情報にも変化がありました。
2014年
新しいタイプの商標の保護制度開始
2015年
特許庁 特許電子図書館サービス(IPDL)からJ-PlatPatへ
2015年
特許事務所向け特許管理システム「PATDATA」の販売・保守サポート開始
2017年
ブランディング部発足(商標事業強化)・「Brand Mark Search」サービス開始
商標事業の強化として専任部門を設立。
「Brand Mark Search」「商標調査サービス」等、これまでと異なる市場開拓にチャレンジ。
これまで培った検索技術と商標独自の考え方を組み合わせたものを柔軟に構築していきました。

BMSサービス開始当時イメージ
2018年
「NewCSS」クラウドサービス開始
2019年
書誌・経過情報に関するデータの切り替え(整理標準化データ→特許情報標準データ)
2020年
特許管理システム「PatentManager」販売開始
2021年
クラウド知財管理サービス「IP Drive」 サービス開始
知的財産管理システム「IP Vision」発売
2022年
公報システム刷新により公報が毎週発行から毎日発行へ
意匠・商標データのXML化
更なるテクノロジーの進化
AIの進化などにより、さらに便利な機能・サービスがこれからも提供されていくでしょう。
2024年
JP-NET・NewCSS・BrandMarkSearchにAIを活用した検索・表示機能を追加

 沿革
沿革